- 橘川 徳夫
- 2024年10月9日
- 読了時間: 3分
「スポーツの秋」がやってきましたね!私もランニングを始めてもう15年ほどになります。最近は1キロあたり5分ちょっとのペースで、月間平均で約80㎞くらい走っています。(走る人にはこの速さがどれくらいか、なんとなくわかるかもしれませんね)。
ランニングを始めたきっかけは、知り合いがマラソンをやっていると聞いたことです。「自分も試してみたい」と思い立ち、走り始めました。途中、数年間休んでいた時期もありましたが、引っ越してから家の近くによい公園があり、再び走りやすい環境が整ったので、また続けられるようになりました。
よく「走って何が楽しいの?」と聞かれるのですが、これって好き嫌いの話と同じで、嫌いな人にはどれだけ説明しても伝わりにくいんですよね。例えば、好きなタレントや俳優がいるとしても、その理由を他の人に説明するのは難しいですし、相手に理解してもらえても、その人が同じように好きになってくれるわけではないですよね。
実際、自分でも「何が楽しいのか」と言われると、うまく説明できないんです。ただ、続けられた理由として思い当たることはいくつかあります。
まずは「時計」です。タイムを測るようになり、少しでも速く走れると嬉しくて、また走りたくなるんです。ランニング用の時計を使うとラップタイムもわかるので、より自分の走りが見えるようになりました。
次に「スマホアプリ」です。ランニングの記録が簡単に取れるようになり、タイムが残るので、走った距離やペースが一目でわかります(あまり深くは分析していませんが……)。
そして「レースへの参加」です。東京マラソンに当選して参加できたことがきっかけで、走る楽しさに目覚めました。コロナ禍の影響でレースが減り、最近は参加できていませんが、「レースに出る」という目標ができたことで走るための意欲が高まったのは事実です。
ランニングを始める理由やモチベーションは人それぞれ。ダイエットや運動不足解消を目的にする人もいれば、かっこいいシューズやウエアをきっかけに始める人もいるでしょう。私の場合は、たまたまランニングに出会った感じですが、実際にやってみないと自分に合うかどうかはわかりませんよね。
ランニングが続けられたのも偶然の出会いですが、これはPRにも通じるところがあると思います。自分が興味のないことでも、まずはやってみる。これが新しいことを知るきっかけになります。PRに携わる皆さんも、知らないことに積極的にチャレンジするのをお勧めします。
走るのが苦手な方も、まずは一度走ってみてはいかがでしょう?もしランニングが自分に合わないと気づいたとしても、それは大切な発見だと思いますよ!(笑)


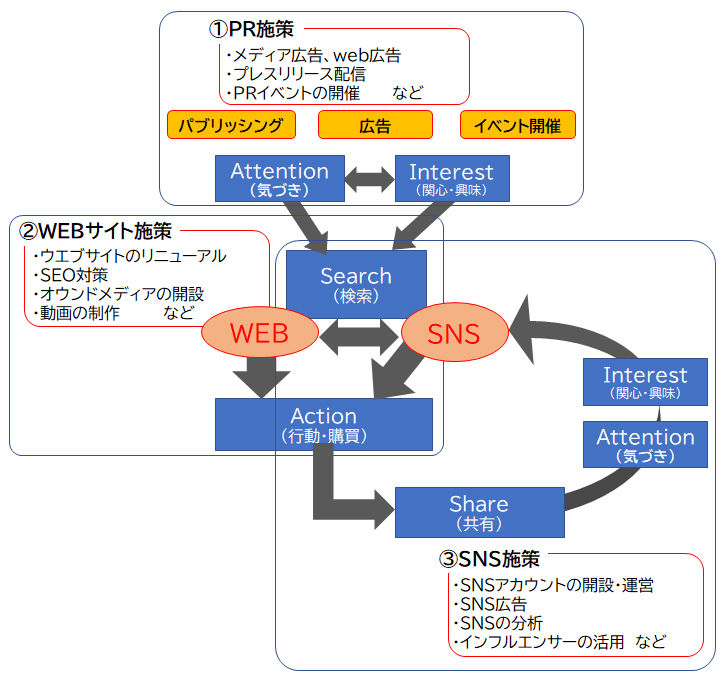
.jpg)